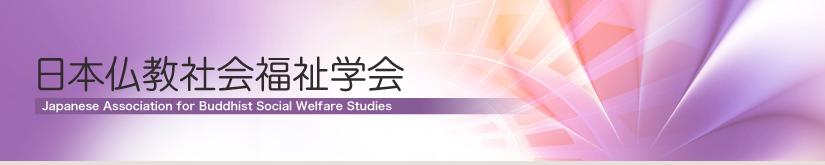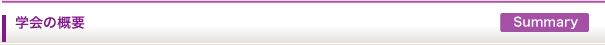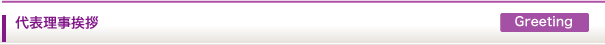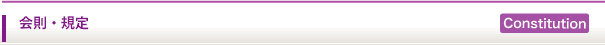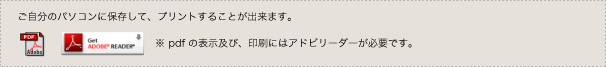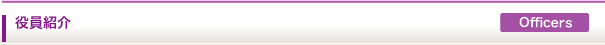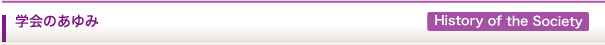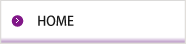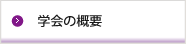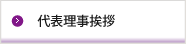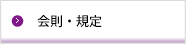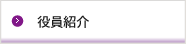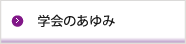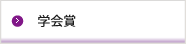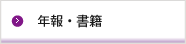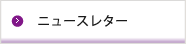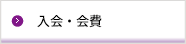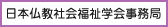昭和41年6月11・12日、日本印度学仏教学会の第17回学術大会(於高野山大学)において、「応用仏教学」部門が新設されることになったのを機に、かねて仏教社会事業の研究と推進とに関心を持っていた関係者が蹶起して日本仏教社会福祉学会を設立することとなりました。設立総会ならびに第1回大会は同年11月11日、立正大学にて開催されました。設立趣意書には「我々は、仏教社会福祉の学術的研究を進めるとともに、社会福祉施設や社会福祉に関係づけられている多くの人々の経営や生活の中に、仏教的なあり方を究明し、把握し、さらにこれを実践的に普及啓発して、姿ないし状態そのものが仏教によって生かされてゆくように望みたいのである」と設立に込められた思いが記されています。
日本仏教社会福祉学会会員の皆様
この度、2023年4月1日より3年間本学会代表理事の任を担う事となりました、藤森雄介と申します。本学会には平成1998年に入会させて頂いてから、永く自身の研究の機会を頂ける場としてお世話になってまいりました。今回の選挙結果を受けて代表理事という重責を担う事に少なからず戸惑いもありましたが、私に投票して頂きました方々を始めとする皆様の期待に応えられるよう、職責を果たしていきたいと考えております。
少し私的な事を述べさせて頂きます。私の研究の出発点は、福祉思想史や施設形成史と言ったいわゆる歴史研究ですが、2011年3月11日の東日本大震災以降は、現在進行形で実践の場に関わる寺院や僧侶の活動にも目を向ける事となりました。また同期間、仏教を主たる宗教とするアジア諸国のソーシャルワークを調査していく中で、その発展・展開に「仏教」の可能性が大いにある事を学ぶ機会を得ました。
そのような学びを通じて、仏教ソーシャルワークは日本のみならずそれぞれの国で歴史的背景を持ちながら連綿と現在に引き継がれ、更に未来への可能性を持ち得ていると感じています。そしてそれをどのように共有し、かつ深広させていく事ができるのかと考えたとき、本学会の果たすべき役割は非常に重要だと思うのです。
一方、コロナ禍での混乱もありましたが、会員数の減少や学会活動の停滞、『年報』掲載の論文数の状況等、ある意味、本学会を取り巻く現状は深刻です。
この現状に向き合い、行うべき改革は行い、本学会を、日本を含めたアジアの国々の期待に副えるような組織に立て直していく事が私に課せられたミッションであると考えています。
その為には、理事・役員の先生方だけでなく、会員の皆様全てのご理解とご協力が不可欠であります。
今後会員の皆様には従来のご連絡以外にも様々な情報発信や、場合によっては本学会活性化に向けたご協力やお願い等も適時行っていきたいと考えています。
これからの3年間、何卒宜しくお願い致します。
日本仏教社会福祉学会代表理事 藤森雄介(淑徳大学)
日本仏教社会福祉学会 役員
(任期:令和5(2023)年4月1日より令和8(2026)年3月31日まで)
- 代表理事 藤森雄介
- 清水 海隆(立正大学)
- 栗田 修司(龍谷大学)
- 池上 要靖(身延山大学)
- 長崎 陽子(龍谷大学)
- 郷堀 ヨゼフ(淑徳大学)
- 吉水 岳彦(浄土宗光照院)
- 団体理事 大正大学 宮崎 牧子
- 団体理事 龍谷大学 児玉 龍治
- 団体理事 淑徳大学 渋谷 哲
- 団体理事 立正大学 武田悟一
- 理事事務局担当 渡邉 義昭(東京YMCA)
- 監 事 山口 幸照(種智院大学)
- 監 事 小笠原 慶彰(神戸女子大学)
本学会は、1966(昭和41)年、創立総会・第1回大会(大正大学)から年1回、全国各地で学術大会を開催し、広く交流の場を設けながら研究を深めてきました。2015年には第50回大会「アジアのソーシャルワークにおける仏教の役割」を淑徳大学で開催し、2016年には50周年慶讃法要並びに記念大会「仏教社会福祉の展望と課題」を立正大学で開催しました。
本学会は、50有余年に渡り、「仏教社会福祉に関する学術的研究及び仏教社会福祉事業の推進を目的とする」学術団体として社会に貢献してきました。
次の50年に向けて歩み、本学会はこれからも、人類の誠の福祉の実現のために、仏教精神に学びながら、皆さまと共に歩みを続けてまいります。
過去の大会テーマは以下をご覧ください。
日本仏教社会福祉学会 大会テーマ一覧